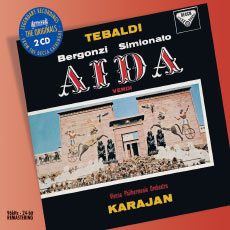カラヤンは、戦後ドイツの軌跡における経済復興を象徴する音楽家だ。カラヤンは他の誰にも真似できないほどの鋭敏さでこの重要な時代の到来を予測して深く理解し、それを立ち姿(異常なほどの綿密さをもって50年代末に形づくり、維持してきた)やメディア対応、レコード販売の世界戦略に反映させてきた。指揮をして録音するだけでは満足しなかったのである。その情熱はサウンド·エンジニアやレコーディング·ディレクター、映画監督、音楽祭や音楽院の創設などの仕事にまで及んだ。スポーツカーを乗りこなし、飛行機やヨットまで操縦し、テクノロジーに対する関心も常に失わなかった。しかしそんなライフスタイルも、カラヤンの真の天職を覆い隠すことはできない。カラヤンは何にも増して、数十年にわたってクラシックの数々の最高傑作を自分のものとすることに成功し続けた、傑出した音楽家であった。
『ベートーヴェン:交響曲第5番』ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団、ドイツ・グラモフォン(以下、DG)(1962)
カラヤンを初めて聴くという人への一番のお薦めは、繰り返し登場する大作曲家ベートーヴェンのDGにおける最初の曲集から、やはり交響曲第5番であろう。揺らぐことのない方向性、峻厳とも言えるコントラスト、表現の強度、どれをとっても圧倒的な上に、この録音からは厳然たる事実を突きつけられる。つまりこれこそがカラヤンであり、ベルリン·フィルこそカラヤンのオーケストラだということだ。ここからは自らの力に酔いしれるカラヤンの麗しい姿が見てとれる。カラヤンによる最初の録音(モノーラル、EMI/ワーナー、1948年)ではウィーン·フィルハーモニー管弦楽団とのめくるめく演奏とカラヤンの詩的な一面を聴くことができる。その後の数々のスタジオ録音は、その再解釈とも言える。また交響曲第4番(DG、1962年11月)も聴きものだ。また、カラヤンとベルリン・フィルの真に野生的な魅力を感じたいのなら、フランスの映画監督アンリ=ジョルジュ・クルーゾーがモノクロのフィルムに音の宇宙を映しとった交響曲第5番は必聴である。
『ブラームス:交響曲第2番』ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団、DG(1963)
カラヤンが繰り返し録音したもう一人のアイコン、それがブラームスだ。ベートーヴェン同様、1960年代以降の各年代に新たなバージョンが残され、まさにカラヤンのライフワークの一つと言える。時間が経ってから聴き直してみると初期のものが基準となり、カラヤン自身がそれを更新し純化させ続けつつ、最初の音を忘れずにいたことがうかがえる。さらに言えば、60年代というのはカラヤンがベルリン·フィルと演奏するようになって約10年が経とうというころだということも影響しているのだろう。そしてなんといってもカラヤンのきわめてこまやかな感覚とオーケストラの豊かなサウンドを通して、ブラームスの曲の持つすべての要素がなめらかに一体となり、極上の作品として結実しているのだ。そこにはノスタルジーと混じり合った詩情が溢れているが、同時に独特の威厳もある。
『ブルックナー:交響曲第8番』ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団、DG(1988)
粘り強く全力で取り組むことを常に要求するブルックナーの素晴らしい交響曲に、カラヤンはいつも惹かれていた。”通常の”9つの交響曲をすべてベルリンで録音していたら、カラヤンはそのすべてをコンサートで演奏することはなく、最後の三部作(第7番、第8番、第9番、そしてテ·デウム)に力を注いでいたことだろう。カラヤンの晩年の諸作と同様、あふれるようなパワーに代わって内面的な表現が前面に立ち、そこには明らかに晩年のカラヤンを苦しめた病の苦しみが暗示されている。カラヤンのアプローチは冷徹で瞑想的だが(アダージョだけでも25分をかけている)、表現には勢いがある。カラヤンがベルリンに次いで愛したウィーン·フィルの輝かしい音は和音の柔らかい響きによってこの冷徹な大理石に声明を吹き込み、すべてを超越して神の許しさえもたらす。すべてが達成され完成されたものが、カラヤンの死後に発表された最終作品、交響曲第7番である。
『ショスタコーヴィチ:交響曲第10番』ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団、DG(1966)
カラヤンは、自身のロシア音楽のレパートリーについて語るときはいつも言葉を慎重に選んでいた。一番のお気に入りはチャイコフスキー(そして自身のキャリアを通じてロンドン、ベルリンそしてウィーンで再演を重ねた)で、それに続くのがムソルグスキー、リムスキー=コルサコフ、プロコフィエフ、ストラヴィンスキーだ。ショスタコーヴィチの交響曲第10番の最初の録音時には戦争を契機に生み出された作品への関心を示し(ニールセン、ホルスト、オネゲル、プロコフィエフらも同様)、1960年代のベルリン·フィルの個性的で濃密な音でそれを具現化した。この芳醇で充実した音は、ロシアにありがちな金属的で耳障りな音と混同してはならない。カラヤンはその才をもって、けっして緩むことのないテンションを保ちながら冷たく悲劇的な世界を描き出している。2回目の録音(DG、1981年1月)はやや粗削りで、曲からいくぶん距離を置いたアプローチが感じられる。何をおいても聴くべきなのは、ショスタコーヴィチ本人の前で行われた1969年の『カラヤン·イン·モスクワ』だ。これはカラヤンの中でも傑出したパフォーマンスの一つとなっている。
『マーラー:交響曲第9番』ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団、DG(1982)
マーラーは、カラヤンのキャリアの歩みの中でも特別な地位を占めている。キャリアの最終盤になってようやく現れたのだ。これはユダヤ人であるマーラーがナチスによって演奏禁止になっていたためと思われる。交響曲第9番を2回録音しているが、その間隔はわずか2年だ。スタジオ録音の後に行われたコンサート(カラヤンは曲をコンサートで演奏する前にレコーディングを行うことが多かった)は絶賛を集め、綿密な準備のもとで行われたライブ録音が後にリリースされた。いずれのバージョンでも、巨匠のタクトのもとで奏でられた見事なサウンドを聴くことができる。いずれもマーラーに敬意を表しつつも後期ロマン派のデカダンスにあふれ、悲劇的な響きを純粋な美へと昇華させている。スタジオ盤(1979年11月と1980年2、9月)ではシュトラウスの影響も醸し出されている。複雑で緊張感に溢れるライブ盤は未来への視線も感じさせる。それぞれを比較しながら双方を満喫することができるのだ。
続きを読むには、無料のアカウントを作成してください